相手に気持ちよく話してもらう。インタビューに臨む心得

しっかりと準備をして臨んでも、取材対象が「人」であるため、場のコントロールに腕が試されるインタビュー。相手に気持ちよく話してもらい、良質なコンテンツのための「素材集め」をするために、知っておきたい心得やコツをご紹介します。
インタビューの流れ
挨拶が済んだら、インタビューに入る前に、念のため今回の取材の主旨を相手に伝えましょう。どういった媒体に、誰を読者ターゲットとして、何を目的に記事を載せるのか。インタビュー前に改めて確認しておくことで、「この時間が何のためにあるのか」をお互いにはっきりと認識することができます。スムーズに本題に入ることができ、本質的な質問もしやすくなるので、「素材集め」の生産性も高まります。
取材中は、できるだけ具体的な話が聞けるように質問を掘り下げましょう。1つの事象の背景には、それを裏付ける具体的なエピソードが潜んでいることが多いものです。
そのため、「面白いエピソードが眠っていないか!?」という意識で、質問を掘り下げましょう。
- これに対してどういうお考えですか?
- なぜそう思われるのですか?
- 過去に何かあったのですか?
- 今後はどうなさるおつもりですか?
また、現在、過去、未来という時間軸も意識していくと、相手も話しやすく、聞く側も話の概要が掴みやすくなります。
タイムマネジメントは必須スキル

インタビュー中に神経を巡らせるのは、会話だけではありません。時間配分にも十分に気を配りましょう。それは、忙しい時間を割いて取材を受けてくれる相手への当然の配慮であり、「お互いの時間を大切にする」という基本的なビジネスマナーでもあります。
時間を正確に計ることができる腕時計かタイマーを持参して、会話の最中もしっかりタイムマネジメントをしてください。
問われるコミュニケーション力。話してもらうにはコツが要る
「取材の承諾を得た」ことと、「話してくれる」ことは、同義ではありません。
もし、取材を受ける側が「どうしてこの人に話さなきゃいけないの?」、「この人には話したくない」と思えばそれまで。こちらが聞きたい話は聞けません。つまり、相手から信頼してもらえないと、聞きたい話は引き出せないのです。
といっても、最初に触れたとおり、挨拶や言葉遣いといった「当然ながら気をつけたいこと」をきちんと踏まえれば、最初の「掴み」はだいたいクリアできるものです。
もう一つ注意したいのは、「取材時の態度」。気をつけたい点をいくつか挙げてみましょう。
相手に興味をもって話を聞く
自分に関心をもってくれている、面白そうに話を聞いてくれている。これは誰だってうれしいもの。相手も気持ちよく話してくれる確率が高まります。間違っても、退屈そうにしたり、眉間にしわを寄せて話を聞いたりしないようにしたいものです。
「知ったかぶり」はご法度
相手に話を合わせようと思って、何となく、とっさに取ってしまう態度かもしれませんが、「素材を集める」という取材においてはご法度。仕事として失格ですし、単純に相手にも見抜かれて信頼を失います。
自分の話はしない
話を聞く側にもかかわらず、貴重な取材時間中に、持論をとうとうと話す人がいます。はっきり言って、あなたの話は聞いていない。取材を受ける側はもちろん、編集者もそう思っているはずです。「どう思いますか?」と意見を求められたとき以外は、持論の展開は慎みましょう。
不測の事態はどうするか
ときに寡黙な人、気難しい人、話がよく脱線する人にインタビューすることもあるでしょう。肝心なことがなかなか聞けないまま、時間だけが過ぎていく…。いわゆる不測の事態です。こういった事態は避けたいものですが、相手は人。信頼関係を壊しかねない強引なことは、なかなかできません。
そんなときには、いくつか乗り切るコツがあります。
寡黙な人や気難しい人の場合には、まず相手の話を遮らないこと、しゃべりたくなるまで待ってみること。そして、「これだけは聞いておきたい」という質問をしっかりと整理した上で、切り口を変えながら繰り返し投げかけてみることです。
話がよく脱線する人の場合には、思い切って「あの、すみません」と遮りましょう。勇気が要りますが、これもお互いの時間のためと割り切る必要があります。
おわりに
インタビューを終えたら、御礼とともに今後のスケジュールについて説明しましょう。
インタビューといえど、基本は人と人とのコミュニケーションです。緊張したとしても、しっかりと目を合わせて、会話を楽しむくらいの気持ちで臨みましょう。
そして、聞きづらい質問にもきちんと切り込むこと。自分を捨てて、「読者なら、こういうことが知りたいと思います」と切り出すことで、本音で答えてくれるケースも多いものです。
No related posts.
関連記事Related Articles
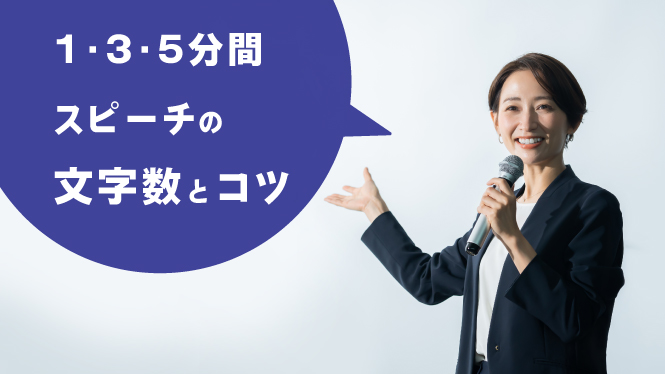
1分間スピーチ・3分間スピーチ・5分間スピーチの文字数とコツ
スピーチ中に焦りを感じたために、口調が早くなったり話す内容が支離滅裂になったりした経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 講演...
お役立ち
インタビュー記事作成時のレイアウトと書き方の注意点
編集者やライター業務においては、インタビューした記事を文章に起こす作業も多く発生します。質の高いインタビュー記事を作成するためには、いくつか...
お役立ち
